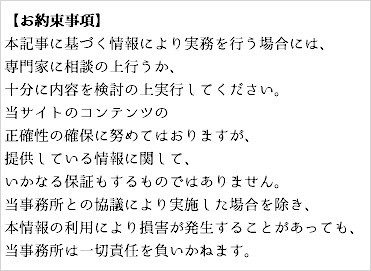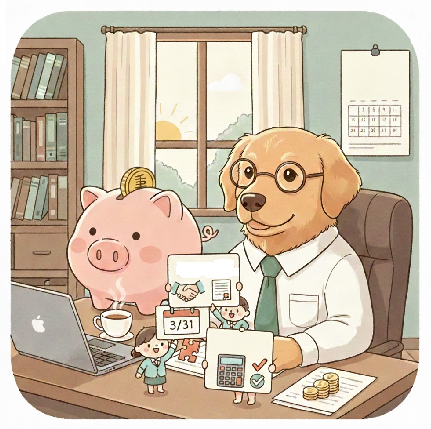
法人税の実務において、重要でありながら判断に迷うことが多いのが「どのタイミングで費用(損金)を計上できるか」という問題です。会計上は費用として計上していても、税務上の「損金」として認められるためには、期末までに「債務が確定」していなければなりません。
今回は、法人税法基本通達2-2-12を軸に、損金算入の根幹となる「債務確定の三要件」について、逐条解説の注釈や専門書の見解を交えて解説します。
まず、法人税法第22条第3項では、損金の額に算入できる範囲を以下の3つに区分しています。
第一号: 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
第二号:前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
第三号: 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
ここで重要なのが、第二号のカッコ書きです。『期末までに債務が確定していないものは除く』とされているため、いわゆる期間費用(販売費や一般管理費)については、別段の定めがある場合を除き、期末までに債務が確定しているものに限って損金算入が認められます。
では、どのような状態を「債務が確定した」と判断するのでしょうか。法人税法基本通達2-2-12では、以下の3つの要件すべてを満たす必要があるとしています。
これは当事者間で債権債務の存在が認識されている状態を指します。民法上、一般的には給付契約の成立がこれに該当します。
単に契約があるだけでなく、期末までに具体的な給付原因となる事実(例えばサービスの提供を受けるなど)が発生していなければなりません。実務的には、”相手方が義務を履行し、自社が支払請求を受けるべき状態(相手方においては収益を計上しなければならない状況)になったことを指します。
金額が絶対的な確定額である必要はありませんが、相当程度正確に見積もることができる必要があります。金額の算定が著しく困難な場合は、要件を満たしません。
専門書『法人税基本通達の疑問点 4訂版(渡辺淑夫著)』では、この三要件を実際の取引に当てはめて以下のように詳細に解説しています。
例えば、6か月間の市場調査を依頼し、毎月一定額を支払う契約の場合、毎月末に役務提供を受けた事実が発生しているため、原則として毎月の債務が確定し、損金に算入できます。 しかし、調査結果を「報告書」としてまとめて受け取る契約の場合、報告書を受領するまでは「給付原因となる事実」が発生したとは言えず、受領時まで債務は確定しません。
3月31日から4月1日にかけて社員旅行を実施した場合、旅行代理店に一括で支払っていても、費用の内訳(宿泊費、交通費、見学料など)ごとに判断します。
”3月31日までに役務提供(宿泊や移動)が完了した部分については債務が確定していると認められますが、4月1日に係る部分については、当期の費用として計上することは認められません。”
研修期間が数期にわたる場合、研修の終了をもって「具体的な給付を受けた」とみなすのが一般的です。 そのため、期末時点で進行中の研修費用は原則として「前払金」として処理し、研修が終了した時点で全額を費用計上することになります。ただし、初級・中級・上級のようにグレードごとに明確に区分されている場合は、それぞれのグレードが終了した時点で費用化することも認められると考えられます。
通常、(1)と(2)の要件を満たせば金額も算定できるのが一般的ですが、鉱害補償のように、因果関係は明確でありながら期末時点で補償金額の算定が客観的に不可能な場合は、例外的に(3)を満たさず損金算入できないことがあります。
「債務確定」の判断を誤ると、税務調査で損金算入時期を否認され、追徴課税(過少申告加算税や延滞税)の対象となるリスクがあります。 特に期末間際の契約や、長期間にわたるサービス契約については、「いつ、どの事実をもって給付が完了したと言えるのか」を契約書や実態に基づいて慎重に精査しなければなりません。
今回ご紹介した指針は、あくまで原則的な取扱いです。具体的な取引内容によっては、個別具体的な検討を会計士・税理士先生とすることをお勧めします。
【出典・参考資料】 *:『法人税通達逐条解説Digital』注釈 1(基通2-2-12関連) *:法人税法基本通達 2-2-12(債務の確定の判定) *:同通達(1)〜(3)要件 *:渡辺淑夫 著『法人税基本通達の疑問点 4訂版』(ぎょうせい)156-157頁(問139, 140) *:同上 158-159頁(問141, 142, 143) *:同上 160頁(問143 続き)